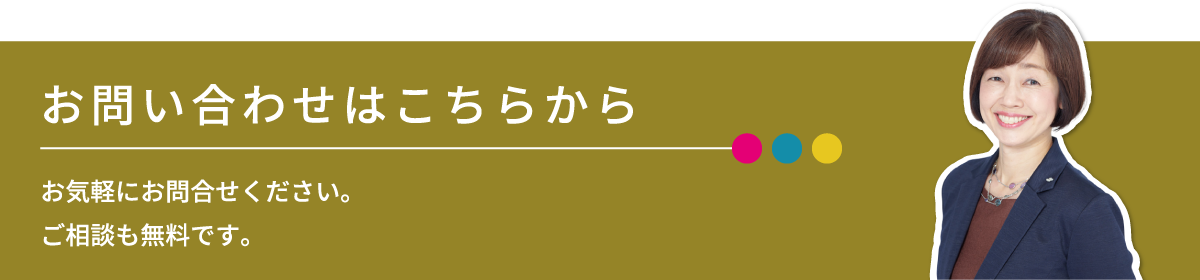先日、ご相談をいただいた企業様のお話です。
その会社では、すでに多くの取り組みが進んでいました。
・お客様満足を高める付加価値づくり
・情報共有とコミュニケーションのICT化
・残業削減に向けた生産性向上
・作業環境の整備と不満の解消
・専門知識を高める社員教育
・評価制度や福利厚生の構築・拡充
など他にもいくつもあります。
直接費も間接費も、決して小さくない投資です。
投資にはリターンがあるはず。
そして、売上や社員のエンゲージメントも比例して伸びていく。
普通はそう考えますよね。
それでもご相談をいただいた理由は、、、
「良い会社にしたいから、できることはやっている。だけど、何をこれ以上すればいいのか分からない。社長の想いが社員に届かず、思うような会社像に近づいていない。売上は悪くないが、やっている割に成果が伸びない。正直、”こんなものか”と諦めかける瞬間がある。成果が出ないと、つい社員のせいにしたくなる自分もたまにいる。それではダメだ。だからこそ、やるなら本当に成果につながる取り組みにしたい。」でした。
実は同じ感覚を、言葉にせず心の中で抱えている方は少なくありません。
なぜか。
原因が見えにくいからです。
「やるべきことはやっているのに、なぜ?」と。
この状態の正体は、とてもシンプルです。
1つひとつの施策には目的があり、単体では正しい。
けれど、施策同士が“つながっていない”のです。
孤立しているため、効果が限定的になり、全体の成果として感じづらい。
いわば、もったいない状態です。
では、どう抜け出すか。

鍵は「橋を架ける」ことです。
施策と施策、想いと現場、学びと実務。
その間に橋を架け、強化していくことで、組織は一体として動き出します。
一例をあげると、、、
・社長の言葉が届かない
社長と現場をつなぐ“翻訳と伝達の橋”
→ミドルの役割、会議の見直し、ビジョンと目的目標と行動の一貫性を持たせるなど。
・ICT化したのに生産性が上がらない
手段と目的をつなぐ“活用設計の橋”
→誰が・いつ・何の成果のために使うかを業務フローへ落とし込む。
・学んだ知識が使われない
学習と実務をつなぐ“運用の橋”
→OJT設計、評価・昇格基準との接続、キャリア支援、ペア実践の場づくり。
当たり前に見えますが、ここが難所です。
難しいから後回しにすると、せっかくの投資が点のまま終わります。
今あるリソースに“てこ(レバレッジ)”を効かせるには、橋の設計と強化が不可欠です。
せっかく取り組んでいるのだから、もっと活かしたいですよね!
今ある施策と資源をつなぎ直し、成果が波及する“連動の回路”をつくる。
これが、組織強化のポイントの1つです。
あなたの会社でも、橋を一つずつ架けていきませんか。
それにより、成果は静かに、しかし確実に加速します。
(文:菅生としこ)