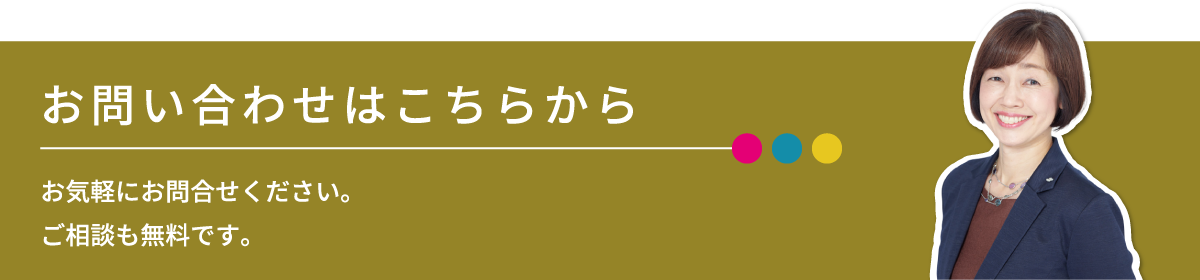部下育成力は、今の時代、必須のスキルですよね。
皆さんの周りにも部下を育てるのが得意な人と苦手な人がいると思います。
よくお伺いするのが、「彼は優秀なんだけど、部下育成が苦手だから、誰を部下につけようか困っています」という話。
残念なことに、部下育成が苦手な人が育成できるようになることを諦めてしまっている、のです。
誰を部下につけようか困る前に、彼が部下を育成できるようにしましょうよ、といつも思うわけです。
優秀な方が部下育成できるようになったら最強です!
部下育成ができる社員が増えれば増えるほど、会社は安泰です。会社全体の底上げができますし、仕事を部下に任せることができた上司は、新たな取組や、今までやれなかった改善活動や、本来すべき未来を考える時間を作ることができ、会社は必ず成長するのです。
では部下育成はどのように行ったらよいのでしょうか。
多くの人が何気なく行っているのは殆どが「ティーチングと呼ばれるやり方を教える」方法です。
部下育成はティーチングをすることだと思っている方も多いのですが、実は、ティーチングは部下育成の一部分であり、ティーチングができたからといって部下育成がうまくできるわけではありません。
では、何をしたら?
部下育成ができるようになる社員を育成するプログラムは、非常にオファーが多いです。
ある企業さんでの出来事です。
プログラムをスタートしたばかりの頃、
A課長から、「部下のB主任は、怒りっぽく、いつも不満ばかり言っている、自分で動かず、課長何とかしてくださいといつも頼ってくる、どうしたらよいか?」と相談をいただいていました。
B主任を育てるのは無理です、と断言されていました(笑)。
ですがプログラムが始まって3ヶ月経ったA課長さんとの面談で嬉しい話をお伺いしました。
「以前、先生に相談していた、困ったB主任の件ですが、
最近、『僕から〇〇さんに連絡しておきましょうか?』など自分から動いてくれるようになったんですよ。
しかも、会社の利益を考えてくれるようになって。
この前なんて『お客さん都合で現場が止まったけれど、作業員の確保を既にしているので、お客さんにその分は支払ってもらえるかどうか僕から交渉しておきましょうか?』
なんて言ってくれるようになったんです。あのB主任がですよ!」
と喜んで報告くださいました。
実は、このA課長も周りからは、いつもぷりぷりして怒りっぽくて、口調は厳しく、話しかけにくい、怖いと評判で、部下を育てるのは無理だ、と思われていた方でした。
そのA課長が困った部下を育てられるようになったのです。
A課長に、「うまくいくようになったのは、何を変えたから?」と聞いてみました。
答えは「自分からなるべく関わる(コミュニケーションを取る)ようにしたからかな」とのこと。
私たちは、あいつは全然仕事をしないとか、怒りっぽいとか、マイナスの色眼鏡で見始めるとよい所が見えなくなります。
それどころか、だんだんと関わりたくないと思い、距離を置くようになります。
A課長には以前、「B主任のことをどんな人だと思っていますか?B主任とはどんな関わりをしていますか?B主任はあなたのことをどう見ていると思いますか?」と質問したことがありました。
それからです、A課長が変わり始めたのは。
何をしたかというと、私はA課長に、〈B主任への関わり方・コミュニケーションの取り方をティーチング〉しながら、〈コーチング〉(1on1面談)をしたのです。
A課長もB主任にコーチング的関わり方をするようになりました。

部下育成を行うには、ティーチングとコーチングの組み合わせが最強です。
そのおかげで育成が苦手だった管理職が、育成が上手になった事例は数知れず。
一緒に働きたくない上司NO,1から、一緒に働きたい上司NO,1に変わった、というすごい方もいます。
その輝かしい成長をされたご本人は「早くプレイヤーから離れて、マネジメント・部下育成に専念したい。僕がプレイヤーをしている限り、部下が育たないから」とおっしゃるようになり、以前は120%プレイヤーでしたが、今は90%マネジメントを行えるようになり、部下に育成の仕方を教えるほどです。
その職場では仕事のプロセス変更ができ、成果が爆上がりしましたし、メンバーのモチベーションがあがったのは言うまでもありません。
人は何歳からでも変われます。
育成が苦手な人は、育成の仕方がわからないだけなのです。
そして、支援者がいることで、成長が加速するという研究結果も出ています。
管理職が部下を支援することで、部下の成長が加速するということです。
あなたの会社の管理職の皆さんは、部下育成はできていますか?
本当に部下が育つ部下育成、始めてみませんか?
絶対オススメは、部下を育てるコーチング・1on1のスキルを磨くことです。
もしも、どのように部下を育てるコーチング・1on1のスキルを磨いたらよいかわからない、という方はご連絡くださいね。
文:菅生としこ